
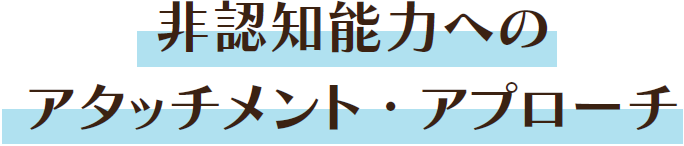

2022 年の「育児セラピスト1 級」に始まり、2024 年の「アタッチメント・ベビーマッサージ/育児セラピスト2 級」と、全面リニューアルを行ってきました。
そして今年のスキルアップ講座は、「キッズマッサージ/アタッチメントジム」の番です。
この10 年で、わたしたちの社会は急速に変化した
アタッチメントにおいて大事なことは、いつの世も変わりありません。それに伴うメソッドも不変のものです。ではなぜリニューアルが必要なのか?
それは・・・「時代が急速に変化しているから」という答えに尽きます。人口減少、少子高齢化、円安、日本経済の下落、それに加えてAIの実用化・・・たった10年の間に、これだけのことが起こっています。当然ですが、社会構造そのものも大きく変化しています。
もちろん、われわれが立っている子育て、保育、教育の現場でも、気づくと気づかないに関わらず、変化の波は着実に押し寄せています。今では、そこかしこで聞かれるようになった “非認知能力(非認知スキル)”と言う言葉と概念は、その変化の象徴であるとわたしは考えています。
これまでの価値観が反転する過渡期に、私たちはいる
わたしが「あそび発達」において非認知能力(非認知スキル)を、みなさんにご紹介したのは、ちょうど10年前の2015年のことです。当時は、J・ヘックマンの研究結果を知っていることは、親としても先生としてもアドバンテージでした。同時に、どこかで「本当にそうなのか?」という気持ちで、みなさんが受け止めていたことを記憶しています。
しかし、10年経った今では、一般のお母さんが非認知能力(非認知スキル)を重視して子育てをしています。もはや一般用語と言ってもよいでしょう。その背景には、さきほど触れた社会構造の変化が関係しているのは、言うまでもありません。

これまで信じてきた教育的価値を捨てきれない
今の親や先生たちは、“非認知能力(非認知スキル)”の重要性を確かに実感しています。しかし同時に、戦後の価値観である通知表や学歴、偏差値などの相反する価値観も捨てきれないままでいます。
子育てや保育、教育の現場では、そんなねじれた理解のもとに、“非認知能力(非認知スキル)”という言葉だけが踊っています。非認知能力をうたいながら、実際には「非認知能力とは因果関係のないことがなされ」ていたり、「非認知能力を育てるには愛情が大切だ」といった抽象的過ぎる解釈で済まされていたりします。

学力を上げ、人生に幸せをもたらす“非認知能力” とは?
非認知能力というのは、その人の性格や考え方、行動における特性です。そのため、数値化して測ることができません。これが原則です。わたしは、この特性を次の5つに分類して解釈しています。
1.やり抜く力(GRIT)
2.集中力(Concentration)
3.自己肯定感(Self-esteem)
4.協調力(Cooperation)
5.コミュニケーション力(Communication)
最近では、さらに6番目の要素として「レジリエンス(乗り越え力)」を足しています。
これらの力が高い子どもは、勉強をやっても伸びるし、スポーツをやっても成果を出す、人間関係もうまく運ぶというわけです。
どうしたら非認知能力を高く育てることが出来る?

見出しの問いこそが、われわれがもっとも知りたいことであり、子育ての方針につながることでもあるでしょう。そのカギは、「体験」にあります。どんな体験かというと、「体からのアタッチメント・アプローチ」による体験です。
だからマッサージですね、スキンシップですね・・・という単純な話ではありません。体験の話です。わたしは、この体験についてドイツ語の“エアレープニス”という概念で解釈しています。
エアレープニスとは、ドイツ語で体験を表わす単語なのですが、一般的な体験とは区別して用いられます。それは、経験をとおして、そこに自分なりの気づきや発見を有するものであり、独自の世界観や物語が存在するもののことを言います。
幼少期に、どれだけエアレープニス的体験(真の体験)をしてきたか。より多くの体験、多様な体験をしてきた子どもは、より高度に、複雑に、広範に、その脳が機能します。そして、ひとつの体験は次の体験につながり、自発的に勉強へのモチベーションさえ生むのです。その結果として、高い非認知能力が育まれます。
「キッズマッサージ/アタッチメントジム」を、 非認知能力の文脈で再構築する

非認知能力を育てる体験のカギとなるのが、幼少期における「体からのアタッチメント・アプローチ」です。そして、それを具体的なメソッドにしたものが、じつは「キッズマッサージ/アタッチメントジム」だったのです。しかし、15年前(2010年)に、この講座をリリースした時には、非認知能力の概念は存在していませんでした。
つまり今回のリニューアルのテーマは、「キッズマッサージ/アタッチメントジム」を、非認知能力の文脈で再構築することです。基本的なメソッドは変わりません。しかしその解釈と理解へのベクトルが違います。
実際、非認知能力という言葉と概念をはじめて持ち出した「あそび発達」のメソッドの中には、キッズマッサージやアタッチメントジムの要素が入っています。非認知能力を育てるメソッドとして最適であると、当時から考えていたからです。
そこで、今回のリニューアルをもって、「キッズマッサージ/アタッチメントジム」を非認知能力を育てるメソッドの決定版とすべく、リニューアルに取り掛かることに決めました。
育児セラピスト2級資格をお持ちの方なら、 どなたでも、再受講でも受講できます
これまでキッズマッサージは、ベビーマッサージ資格をもっている方のみが対象で、アタッチメントジムは、育児セラピスト2 級資格の方が対象でした。今回のリニューアルによって、正規リリース時には、講座の構造そのものが変わり「ベビーマッサージ資格」をお持ちでない方も受講できるようになります。それに合わせて、今回のスキルアップ講座でも、育児セラピスト2 級資格をお持ちの方全員が対象となります。また、すでに資格をお持ちの方も、再受講で新カリキュラムをご受講いただけます。
今回のリニューアルにより、来年から始まる正規講座は、事実上の値上げとなる予定ですので、もしご興味のある方は、今回の全国大会スキルアップにてご受講されることをおすすめいたします。(これまでの受講料のままで、新規で同時受講の方は、セット割引も適用されます。)
古い方々はご承知のことと思いますが、新しい講座は、全国大会スキルアップで受講するのが、料金的にも体験的にも一番得になります。
今年も、東京会場の対面と、オンラインの両方で行います。みなさんとお会いできるのを楽しみにしております。
一般社団法人 日本アタッチメント育児協会
理事長 廣島 大三
リニューアル
AKM・AGM ご受講の流れ

10/4(土)スキルアップ
1日目
オンライン
東京会場(アタッチメント・アカデミア)
時間 10:00 ~ 18:00
- AKM リニューアルコンテンツ
- AGM リニューアルコンテンツ
10/11(土)スキルアップ
2日目
オンライン
オンデマンド(再受講のみ)
時間 10:00 ~ 16:00
- AKM/AGM 既存コンテンツ
- +
- 実技試験 16:00 ~ 17:00
- 学科試験 17:00 ~ 18:00
※新規受講の方は試験あり(~18:00)

「アートと非認知能力の育ち」

保坂 遊 教授
東京家政大学子ども支援学部長
臨床美術士1級
今年の全国大会シンポジウムの基調講演は、臨床美術の観点から造形活動と子どもの発達について研究されている東京家政大学子ども支援学部 教授の保坂 遊先生に、「アートと非認知能力の育ち」をテーマにお話しをいただきます。
保坂先生は、「美術は、生涯、人の生(life)にコミットする精神活動である」という信念のもと、臨床美術・芸術保育の分野で活躍されておられます。とくに、発達グレーゾーンや発達障がい児の療育において、アートセラピーの可能性を追求しておられます。
そんな保坂先生に、アートや創作活動をとおして非認知能力を育てることについてお聞きしたいと考え、このテーマを投げさせていただきました。
幼児教育+リベラルアーツ=非認知能力の爆上がり!
わたしは、そもそも幼児教育にこそ、リベラルアーツの概念を取り入れるべきだと考えています。リベラルアーツのなかでも芸術や音楽、それをとおした自由な創作活動は、子どもの想像力を掻き立て、探求心を刺激し、さまざまな困難に対する問題解決力を養います。こうした活動をとおして、ある一つのことを深く掘っていく楽しさを発見し、最後までやり抜く力や集中力が身につきます。これこそが、リベラルアーツによる学びです。
もうお分かりのことと思います。これは「非認知能力」の話なのです。幼児教育にリベラルアーツを取り入れることは、非認知能力を育てることと同義だと言えます。
ただしこれは、子どもにとって「遊び」でなければ機能しません。「育児セラピスト2級」のテキストを思い出してください。「子どもの活動はすべて、遊びとして体験されなければならない」のです。では、どういうものが遊びと呼べるのか?
「あそび発達」の講座では、遊びをつぎのように定義しています。
『無目的で意味のない子ども固有の行動的な活動』
幼児教育は、子どもに“遊び”を提供できているのか?
幼児教育や、子どもの習いごとは、“遊び”になっていないケースも多いのではないでしょうか。これは、大人は、とかく遊びに「目的」や「目標」を設定してしまいがちだからです。
例えば、“おえかき”をするとします。「手にクレヨンを持って、いろんな色を使って、画用紙に描きましょう」となります。そこで、クレヨンを投げて遊ぶことは想定されていません。手にクレヨンを塗りたくって、紙にこすりつけて描くことも、紙の上でクレヨンを踏んづけて描くことも想定されません。
「音楽に合わせて自己表現のダンスをしましょう」というとき、何もしないでジッとしていることは、許されません。ただ走り回ることは、ダンスとして認められません。その代わりに、まわりと協調した動きを求められるかもしれません。
大人は、想定内の反応を子どもに期待します。悪気があるわけではありません。大人の脳は、目的を設定して、その道筋を立てることに馴れているので仕方ありません。しかし同時に、大人のこうした行為は、子どもから“遊び”の機会を奪っているのも事実です。
目的を設定してしまっては、遊びとして機能しないからです。そうなると、非認知能力の育ちも期待できません。これが、多くの幼児教育や習いごとの現場で起きている現実だと、わたしは考えています。
だからこそ、「リベラルアーツ」という聴き慣れない大層な概念を幼児教育に持ち込む意味が出てきます。この言葉によって、大人にとって“あたりまえ”の思考(脳の働き)をフリーズさせ、遊びを再定義する余地を生もうというのです。

リベラルアーツは、自由な生き方を得るための活動である
ここで言うリベラルアーツとは、その語源であるラテン語のアルテス・リベラ―レス(artes liberales)、つまり「自由人にふさわしい諸学芸」という意味におけるリベラルアーツです。ちなみに、この自由人の完全体こそが、子どもであると、わたしは考えます。
「個人の能力を開花させ、困難や多様性、変化へ対応する力を身につけさせ、科学や文化、社会などの幅広い知識とともに、より深い専門知識を習得させるための学習方法」
日本におけるリベラルアーツの先駆である国際基督教大学が掲げるリベラルアーツ教育のコンセプトです。これは、大学教育だけでなく、幼児教育を含むすべての教育に当てはまるものだと思います。
同時に、このコンセプトは、そのまま「非認知能力」そのものを表現している言葉でもあります。やはり、非認知能力を育てるカギは、リベラルアーツ教育にあると思うのです。
アートは、子どもが自由を得る術なのかもしれない
ここまで、わたしの思考の“遊び”におつき合いいただきましたが、この話に結論を付けるつもりはありません。子どもの発達における未知の可能性の広がりと、リベラルアーツの大きな一翼を担うアートや創作活動との親和性について、話題にあげたかったのです。
健常児と言われる多くの子どもは、クレヨンをもって、画用紙に描く“おえかき”をするかもしれません。しかし、そうではない“おえかき”をする子がいたとき、“おえかき”としては他の子の活動と違っていても、“アート”としてなら、大人もその活動を賞賛できるかもしれません。
リベラルアーツのなかに、芸術や音楽が組み込まれ、欧米を中心に永く教育の中で大切に育まれてきたのは、そういう背景があるのかもしれません。
今年の全国大会シンポジウムでは、アートにおける創作活動と非認知能力の育ちを、その道の専門家である保坂先生から学びたいと思います。
ここで学んだ知識や気づきが、扱いがむずかしい子や、発達が気になる子、問題行動が見られる子と接するときの助けとなるかもしれません。それだけでなく、こうした子どもたちにとっての希望の光となるかもしれません。
わたしは、そんな期待をせずにはいられないのです。
一般社団法人 日本アタッチメント育児協会
理事長 廣島 大三
優秀実践発表

「言葉にして振り返る」ことで開発される AI時代のカギとなる能力=「言語化能力」
今年も、毎度同じことを繰り返しお伝えさせていただきます。
実践報告には、いつも報告者の視点で紡がれた物語があります。その物語には、さまざまな登場人物が描かれ、出来事やアクシデントをとおして、最終的に主人公が成長します。そうした報告者の発表を聴く機会が、優秀実践発表です。これは皆さんにとって、脳への刺激であり、発想の転換であり、モチベーションの源泉となります。
同時に、実践報告は、みなさん一人ひとりが「これまでしてきた実践を言葉にして振り返る」機会でもあります。この「言葉にして振り返る」という作業は、これから迎える「AI時代」において、とても重要な能力を開発してくれます。これからのAI時代のカギとなる「言語化能力」が開発されるからです。
言語化した人にだけ起こるダイナミックな体験と学び
さらに実践報告をした人が、優秀実践者の発表を聞くのと、してない人が聞くのとでは、起こる事実が全く違います。両者の間では、その脳内で起こっている反応の次元が全く異なるのです。
発表者の物語は、聞き手により深く、よりリアルに、より実用的に伝わり、それを自分事に置き換えて解釈することができます。そのため、よりダイナミックな体験となり、大きな学びと刺激と発想を受けることになります。
同じインプットが行われても、受け手によってそのアウトプットは全く異なるのが、われわれの脳の特性です。この事実は、「AI時代」においては、もっと加速することでしょう。
カタチなきものにこそ、本当の価値が宿る
これまでの活動の区切りや振り返りとして、そして、これからの展望を描くため、「実践報告すること」は、この上ない価値を創出してくれます。言葉にしてまとめた時点で、大きな意味が立ち現れます。
さらに、優秀実践者として、それを発表することで大勢の人にアウトプットする機会を得ると、何かのスイッチが入ったかのように、自分のまわりの状況が動き始め、必要な情報が入ってきたり、必要な人と出会ったりします。
これは、社会学者ロバート・キング・マートンの言う“セレンディピティ”や、心理学者カール・グスタフ・ユングの言う“シンクロニシティ”に外なりません。実践報告には、そんな奥深い世界観が確かに存在します。これまでの発表者をみてきて、これは、はっきりと断言できます。
“場” には、想像を超えたチカラがある
実践報告をしたことのない人は、ぜひ今年やってみてください。書くだけで、すでに大きなものが得られます。いまやっていることの価値が実感できます。そして、次にどこに進みたいのかという展望が見えてくることと思います。
実践報告をしたことのある方は、“その後”をつづってみてください。物語のつづきです。すると、自分が確実に前に進んでいることが実感できます。点と点は線でつながり、明確な展望が浮かび上がります。それは、あなたの人生を豊かにしてくれます。
これをやらない手は、ありません
今年はぜひ、実践報告の段階からご参加ください。
育児セラピスト全国交流会
毎年恒例のランチを介した「おしゃべり会」です。いっしょに学んだ仲間との再会であり、新しい仲間との出会いでもあります。お互いの近況や、いま取り組んでいることなどを自由に話し、交流することで、その後につながる関係性が生まれます。
そもそも、全国大会は、講座を修了された方たちが再び集い、しゃべり、刺激を受け、つながり合い、新しい関係をつくるための場です。たまたま、同じグループになった人は、そうなる縁でつながっている人です。何かしら意味があります。ランチ交流会は、その入り口です。じつは、そのあとにおこなわれる「お悩みスーパーバイズ」につながる導入の役割も担っています。

お悩みスーパーバイズ 2025
「お悩みスーパーバイズ」では、お互いの悩みに向き合います。全国大会のように、同じ思い、同じ志をもって、同じ学びを共有している仲間同士が集う場だからこそ、“安心安全の場”が形成されます。
そのような場で、悩みを他者に打ち明ける、他者の悩みを聞く。いろんな人の考え方や捉え方に触れる。それは、人によって、刺激であったり、新たな気づきや解決であったり、あるいはセラピーになったりします。
じつはこれ、アタッチメント理論に基づく心理療法として近年注目されている「メンタライジング」という心理セラピーで起こる作用そのものなのです。
ある人は、刺激をもらうことで、なえかけていたモチベーションに再び火が付くかもしれません。やりあぐねていたことの解決策を得る人がいるかもしれません。気落ちしていた心が、癒されるかもしれません。同じように悩んでいる人に出会い、「自分だけじゃなかった」と背中を押されるかもしれません。
人とつながり、未来とつながり、価値を創出する

わたしは、ここで、スーパーバイザーの役を、毎年させていただくことで、みなさんとの関係性を深め、先の展望を持たせてもらい、明日への活力をいただいております。同時に、参加者のみなさんにとっても、そのような時間となっていると願っております。
わたしにとって、みなさんと直接お話しできる機会は、いくつかの講座と、この全国大会だけです。
いつもいらしてくださる常連の方々の近況を、今年もお聞きしたいです。
そして、まだお会いしたことのない方のお話しを聞きたいです。
みなさんの悩みや課題を、わたしにも、いっしょに向き合わせてください!
